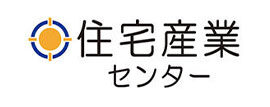住宅ローンの金利は今後どうなる?家を建てるべきタイミングを解説!
住宅ローンの金利は今後どうなる?家を建てるべきタイミングを解説!
住宅を購入、あるいは新築する際に利用される住宅ローンは、金利次第で家計に大きな影響を与えます。
そのための情報収集は、ネット検索や金融機関などが開催する相談会、セミナーが多いと考えますが、用語の理解や金利のしくみについて、知る機会は多くないのが現状です。 そこで今回は、金利の基本知識をはじめ、金利動向、そして専門家の見解や予測、さらに金利変動への備え方などを、お伝えすることにします。
住宅ローン金利の基本知識
住宅ローン金利を知るには、
- 金利決定のしくみと種類
- 金利に関係する用語の理解
については、少なくとも把握しておくことをおすすめします。
そこで本章では、住宅ローン金利とは何かといった基本的な知識や金利の種類、さらには、そのしくみと用語についてお伝えします。
住宅ローン金利って何?初心者でもわかる基礎知識
住宅ローン金利を知るには、
- 金利決定のしくみと種類
- 金利に関係する用語の理解
については、少なくとも把握しておくことをおすすめします。 そこで本章では、住宅ローン金利とは何かといった基本的な知識や金利の種類、さらには、そのしくみと用語についてお伝えします。
住宅ローン金利って何?初心者でもわかる基礎知識
住宅ローン金利は、融資を受けた金額に対する利息の割合です。
利息については、貸した側に支払う賃借料や手数料と解釈すると、わかりやすくイメージできます。
ただし住宅ローン金利を、金融機関の窓口やホームページなどでチェックすると、
- 店頭金利(店頭表示金利)
- 適用金利
という用語が目につきます。
店頭金利(店頭表示金利)とは、いわゆる住宅ローン金利の定価と考えるとよいです。
この定価を基にして、契約者ごとに、
- キャンペーン期間中の申し込み
- 取引実績(給与振り込みなど)
などの条件を満たすごとに、優遇幅と称して金利を引き下げ、契約者ごとに実効的な金利、つまり適用金利が決まります。 適用金利=店頭金利-優遇幅
住宅ローン金利の種類とその仕組みを理解しよう
住宅ローン金利には、主に固定金利と変動金利の2種類があります。
それぞれ、
- 固定金利:10年国債の金利
- 変動金利:短期プライムレート(短プラ)
をベース、商品でいうところの「原価」になる指標として金融機関は注視し、定価である店頭金利を定めます。
固定金利は、契約時に定められた適用金利が、返済期間中は変わらないタイプで、返済額が安定することが特徴です。
一方、変動金利は、市場の動向に応じて金利が変動するタイプで、一般的には半年ごとに見直されることになります。
相対的に変動金利は、固定金利より金利が低く設定されていますが、この傾向に変化はありません。
ただし変動金利は、市場が金利上昇局面になれば金利を見直され、返済額が増えるリスクを抱えます。
その金利の変動リスクを一時的に抑えたい一方で、変動金利の低金利も魅力的であるというニーズに対しては、固定金利期間選択型があります。
一定期間(5年、10年など)固定金利が適用された後に、変動金利へ移行するタイプです。
現在の金利動向と背景
現在の金利動向と背景を知るには、主要なメディアによる解説記事を読むことが、もっともわかりやすくておすすめです。
具体的に挙げるならば、
- 金融機関のホームページにおけるコラム
- 一般財団法人住宅金融普及協会の住宅ローン金利情報
https://www.sumai-info.com/loan-knowledge/kinri.html - ダイヤモンド不動産研究所(アクセスランキング)の上位記事
https://diamond-fudosan.jp/ - 日本経済新聞のマネー知識
https://www.nikkei.com/special/money-knowledge
などで、動向を知ることができます。
今の住宅ローン金利はどうなっているの?最新動向を解説
前述したメディアのひとつを取り上げてみると、執筆時点(2024.7.20)の住宅ローン金利について一部を引用すると、
- 2004年頃をピークに住宅ローン金利は下がり続けている。
- 5年固定、10年固定、35年固定(全期間固定)については、足元では金利が上昇し始めているものの、長期的に見ればまだ低水準。
- 変動金利タイプは、史上最低水準
と述べられています。
引用元
2024年8月の住宅ローン金利(フラット35、変動金利、10年固定)を予想! 金利の推移、今後の金利動向を確認しよう|ダイヤモンド不動産研究所
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/132585
ただし、日本銀行がマイナス金利政策を解除したことによって、金融機関はジワジワと金利を上げていく可能性も否定できません。

住宅ローン金利の現在の状況とその背景
まず、「マイナス金利政策を解除」について簡単に説明します。
金融機関は一定の資金を日本銀行の当座預金に預け入れますが、その際に適用される金利がマイナス、つまり預けても資産が目減りする状況が続いていましたが、それを解除に踏み切ったのが2024年3月のことです。
マイナス金利のとき、金融機関は市場に資金を回して融資を積極的に行う、具体的には住宅ローン金利を低く設定してでも契約を得たほうが利益も積み上がりますし、市場も活性化します。
ところがマイナス金利の解除からプラスへ転じるとなれば、再び、日本銀行の当座預金に預け入れるだけで金融機関は資産を増やせることになります。
一方、市場に回す資金が減ると融資の枠も少なくなり、住宅ローンについては金利を高めに設定して融資の抑制をしたとしても、金融機関として利益は確保できるわけです。
特に変動金利は、半年に1度のペースで金利の見直しが行われるため、マイナス金利解除から半年後の8月や9月以降は、金利上昇に踏み切る金融機関は増える可能性はあります。
金利の変動要因とは?経済状況から見る今後の金利
住宅ローン金利の変動は、日本銀行の政策だけでなく、国内の経済状況も大きな要因となります。
一般的に、国内の景気が好転するようになれば、金利も上昇する傾向です。
ゆえに日本銀行は、3月にマイナス金利政策を解除した後も「現時点の経済・物価見通しを前提にすれば、金融環境が継続すると考えている」とのスタンスでした。
その上で、6月の日本銀行総裁による「(7月までに)出てくる経済・物価情勢に関する情報次第で、短期金利(政策金利)を引き上げて金融緩和度合いを調整するということはあり得る」との発言は、非常に注目されています。
注)
7月の金融政策決定会合は30日(火)と31日(水)に行われるため、執筆時点(2024.7.20)では言及を控えます。
そこで、内閣府の景気動向指数の速報(5月分)を参照すると、「景気動向指数(CI一致指数)は、下げ止まりを示している。」と記されているものの、前3ヶ月(2~4月)の指数はゆるやかに上昇していることから、金利上昇の可能性もあります。
参照元
CI5月分(速報)の概要
https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/202405psummary.pdf
専門家の見解と予測
住宅ローン金利などの動向については、さまざまな見解や予測が専門家から発信されます。
非常に貴重な情報ではありますが、
- だれを信用して良いのか
- どこまで参考にすればよいのか
といった戸惑いもでてきます。
しかし、専門家の見解や予測の情報を持っていれば、判断の材料にもなるため、日ごろから関連メディアに目を通しておくことは重要です。
住宅ローン金利はどうなる?プロが予測する未来のシナリオ
経済評論家などによる金利変動の予測と見解の例として、前述のダイヤモンド不動産研究所では、8月の住宅ローン金利の動向を予測しています。
- フラット35:引き上げ
- 変動金利:引き上げ
- 10年固定金利:引き上げ
急激な金利上昇の可能性は低いとしながらも、景気動向指数や日経平均株価などから景気は回復基調とも読み取れますし、住宅ローンは多くの金融機関にとって収益の中心のひとつにもなっているため、少しでも多くの利益を確保したいと考えと、当然の流れともいえます。
また、先ほども述べましたがマイナス金利の時代が終わり、住宅ローンにも金利が影響を受ける機会は、これからも増える可能性があります。
8月以降については、固定金利の基準ともなる10年国債が2013年以来、1%を超えていることから各金融機関も動き出すことが予想されながらも、依然として低い水準で推移するとの見方も多いです。
変動金利については「据え置きの状況」、10年固定金利は「引き上げの流れが続く」との見解が記されています。
住宅ローン金利変動にどう備える?初心者向け対策ガイド
住宅ローンを組むにあたっては、金利の変動への備え方が重要になります。
特に金利の上昇局面において、固定金利は動向に左右されませんが、変動金利は不安が募ることも考えられます。
ただし、物価も連動して上がる傾向があるため、家計の負担が増える面では、金利タイプで違いはありません。
また、住宅の購入や新築のタイミングなども難しい判断となるため、本章では動向に応じた動き方についてお伝えします。
金利が変わったらどうする?今からできる対策
基本的な対策としては、
- 繰り上げ返済
- 借り換え
- 新たな返済プランの提案を受ける
の3つです。
将来の金利上昇リスクを回避できる固定金利では、何もすることが無いと考えるのは早計で、金利上昇の局面では物価も上がる傾向のため、家計の支出が増えることが予想されます。
そうなる前に繰り上げ返済を行うことで元本と利息を減らしますが、住宅ローン控除や家計の余力を見ながら、繰り上げ返済の金額は調整が必要です。
繰り上げ返済後は返済期間を短くするか、毎月の返済額を減らすかは状況に応じて選択します。
次に借り換えですが、一括返済した後に有利な金利のローンへの切り替える方法ですが、まとまった資金や手続きの費用など、トータルでの損得勘定を明確にするため、金融機関やファイナンシャルプランナーなど専門家との相談は必須です。
繰り上げ返済や借り換えの余力がない場合は、金融機関に返済のプランを提案してもらうことが、もっとも安心できる方法といえます。
住宅ローン契約の前後に関わらず金利の動向に応じて、どう動くのかを情報共有してサポートを受けることが最適です。
住宅ローン金利が上がる前に家を買うべき?こんな人には早めの購入がおすすめ!
金利の動向を読んでの家の購入や新築は、非常に難しいものがありますが、多くの人が悩む部分です。
金利が低い時期に固定金利を選択すれば、将来的な金利上昇のリスクを避けられるため、子どもの教育費や老後の資金計画など、長期的な視点で家計を見直すことも可能になります。
変動金利においても、相対的に固定金利より低い金利、家計の収支状況とリスクも承知の上での決断も間違いとはいえません。
住宅ローン金利が上がることを見越して、
- 安定した収入があり、増加の見込みもある
- 家族が増える予定がある
- 同じ地域で長く住みたい
といった状況ならば、早めの購入はおすすめです。
安定した収入と増加の見込みがあれば、金利が上がっても返済能力に余裕があるため対応が難しくありません。
現在の住環境への不満や住まいの費用が気になる場合は、早めの購入で家族構成の変化に対応できますし、住居費用も抑えることができます。
また、都市部や開発予定の地域の物件であれば、将来的な資産価値の増加を期待できます。
これらの要素を総合的に考慮して、ライフスタイルや将来の計画を基に購入を検討するならば、住宅産業センターまで、お問い合わせください。